●休符
休符についての規則はいたってシンプルです。 休符は縦棒で表されますが、覆っている線間の数がそのまま休止するテンプスの数を表しています。
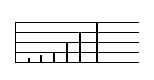
つまり一つの線間を覆っている縦棒はテンプス一つ分の休みを表し、二つ、三つの場合はそれぞれテンプス二つ三つ分の休みを表します。
ここで注意したいのは、テンプス一つ分の休符はブレヴィスの休符、二つ分の休符は不完全ロンガあるいはアルテラ・ブレヴィスの休符、三つ分の休符は完全ロンガの休符を表しているということです。したがって、例えば不完全ロンガの休符が二つの「完全」にまたがるようなことはありません。
また、セミブレヴィス・ミノルの長さの休止は線間の三分の一の線で表されます。セミブレヴィス・マヨルの長さの休止は線間の三分の二の線です。
※このセミブレヴィスの休符に関する規則は、フランコ特有のもので、実際の楽譜で本当にミノルとマヨルを区別して書いているものはほとんど無いのではないかと思います。またアルス・ノヴァ以降のセミブレヴィスの休符の記述はこれとは異なります。
四つの線間全体を覆っているものだけは特殊で、これはフィニス・プンクトールム finis punctorum (終止)と呼ばれ、曲の終わりにのみ使われます。
以下、フランコによる例を挙げます。 (※『計量音楽論』第九章参照。)
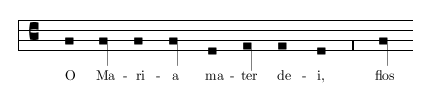
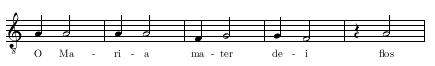
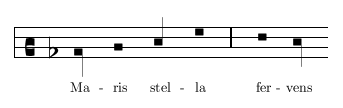
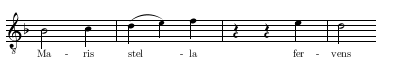
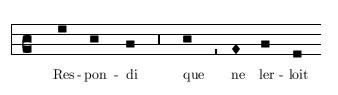
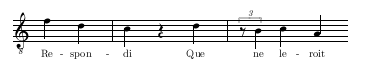
●リガトゥラ
リガトゥラの規則は多少ややこしく見えます。リガトゥラの始めの部分と終わりの部分で規則が違い、上行しているか下行しているかによっても規則が変わります。それらのことは以下で見るように、多少その背景を理解しておくと納得しやすいかもしれません。 (※『計量音楽論』第七章参照。)
まず基本となるリガトゥラがあり、それは次の二つです。
 :下行 B-L
:下行 B-L :上行 B-L
:上行 B-L※は上行を表していて、下から上に読むことに注意してください。
これらのリガトゥラは、もともとグレゴリオ聖歌を記述するネウマであって、それぞれクリヴィス clivis、ポダトゥス podatus と呼ばれるものでした。それが、ノートルダム楽派のモーダル記譜法においても流用され、それぞれの一番目の音符がブレヴィス、二番目がロンガを表すものとされました。
この B-L 以外の組み合わせ(B-B, L-B, L-L)を表すために、上の基本形を変形するというやり方が考案されました。そして、この変形の仕方を表現するために「プロプリエタス proprietas」(=proper)と「ペルフェクツィオ perfectio」(=perfect)という概念が導入されます。
「プロプリエタス proprietas」はリガトゥラの最初の音符についての用語で、最初の音符が上の基本形のようにブレヴィスであるときクム・プロプリエタテ(プロプリエタス付き) cum proprietate と呼びます。逆に最初の音符がロンガであるときシネ・プロプリエタテ(プロプリエタス無し) sine proprietate と呼びます。
一方「ペルフェクツィオ perfectio」は、リガトゥラの終わりの音符についての用語で、最後の音符が基本形と同じくロンガであるときに、クム・ペルフェクツィオネ(ペルフェクツィオ付き) cum perfectione と呼びます。逆に最後の音符がブレヴィスであるときシネ・ペルフェクツィオネ(ペルフェクツィオ無し) sine perfectione またはインペルフェクツィオ imperfectio と呼ばれます。
※英語で言うとcum = with, sine = without です。
さて、それでは、「プロプリエタス」と「ペルフェクツィオ」の有無により音符がどのように変形されるかをまとめてみます。
| 名称 | 音価 | 下行形 | 上行形 |
| cum proprietas et cum perfectione | B-L |  |  |
| sine proprietas et cum perfectione | L-L |  |   |
| cum proprietas et sine perfectione | B-B |  |  |
| sine proprietas et sine perfectione | L-B |  |   |
これだけではわからないので、一つづつ見ていきましょう。
※以下では三音以上のリガトゥラも一緒に扱います。先走って言うなら、三音以上のリガトゥラの中間の音符は、一つの例外を除いていつもブレヴィスになります。
下行形のプロプリエタス
開始部が下行形のリガトゥラで、最初の音符の左の部分から下向きの線が出ているものは、クム・プロプリエタテです。つまり下のようなリガトゥラの開始音は全てブレヴィスです。
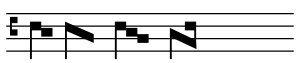
一方、そのような下向きの線の無い開始部が下行形のリガトゥラは、シネ・プロプリエタテです。つまり下のようなリガトゥラの開始音は全てロンガです。
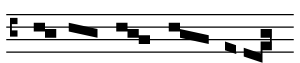
上行形のプロプリエタス
開始部が上行形のリガトゥラの、最初の音符から下向きの線が出ていないなら、クム・プロプリエタテです。つまり下のようなリガトゥラの開始音は全てブレヴィスです。
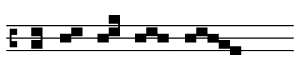
一方、開始部が上行形のリガトゥラの、最初の音符から下向きの線が出ているなら、シネ・プロプリエタテです。つまり下のようなリガトゥラの開始音は全てロンガです。
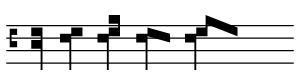
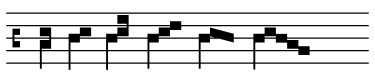
※線が出るのは音符のどちら側もありです。それにしても、上行と下行で規則が逆なのがちょっとややこしいですね。
下行形のペルフェクツィオ
終結部が下行形のリガトゥラの、最後の音符がブレヴィスみたいに普通の矩形をしてる場合、クム・ペルフェクツィオネです。つまり、下のようなリガトゥラの最後の音符は全てロンガです。
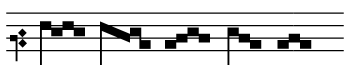
一方、終結部が下行形のリガトゥラの、最後が斜形で終わっているものは、シネ・ペルフェクツィオネです。つまり、下のようなリガトゥラの最後の音符は全てブレヴィスです。
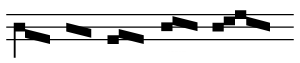
上行形のペルフェクツィオ
終結部が上行形のリガトゥラで、最後の音符がその前の音符の真上にあるとき、クム・ペルフェクツィオネです。つまり、下のようなリガトゥラの最後の音符は全てロンガです。
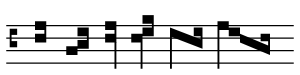
一方、終結部が上行形のリガトゥラで、最後の音符がその前の音符とそっぽを向いているとき、シネ・ペルフェクツィオネです。つまり、下のようなリガトゥラの最後の音符は全てブレヴィスです。
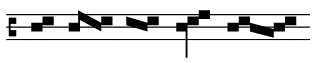
また、リガトゥラの最後が斜形の上行形である場合もシネ・ペルフェクツィオネです。
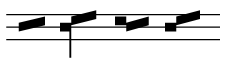
ただ、斜形の上行形は下で説明するプリカの上行形でしか使用されません。
さて上でチラっと言いましたが、原則として
リガトゥラの最初と最後の音以外は全てブレヴィス
です。
ここで例を挙げましょう。
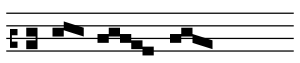
[B-L, B-B-B, B-B-B-B-L, B-B-B-B]
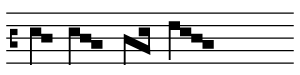
[B-L, B-B-L, B-B-L, B-B-B-L]
上の方の例についてもそれが何を表すリガトゥラかをチェックしてみると良いでしょう。答は『計量音楽論』の第七章にあります。
さて、実はプロプリエタスには上で述べたクム、シネの他にもう一つあります。それは「クム・オポジタ・プロプリエタテ cum opposita proprietate」というもので、最初の音符の左側から上向きに線が出ているものです。
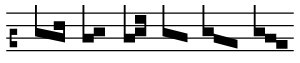
このような場合、最初の音符と二番目の音符がセミブレヴィスになります。したがって上の例では、それぞれ [S-S-L, S-S, S-S-L, S-S, S-S-B, S-S-L] のようになります。
クム・オポジタ・プロプリエタテで、二番目の音符もセミブレヴィスになるのは、「セミブレヴィスが単独では存在できないから」だとフランコは説明しています。そして、このケースが、リガトゥラの中間の音符がブレヴィスにならない例外です。
以上で述べたプロプリエタス、ペルフェクツィオについて表にまとめておきましょう。
|
|
フランコ式記譜法のリガトゥラは、この表と、これ以外の場所ではすべてブレヴィスであるということを頭に入れておけば、バッチリです。
さて、リガトゥラの実際の使用例を挙げます。リガトゥラの中の音符も単独音符のときと同じ規則にしたがうことに注意してください。例えば、ロンガは不完全化します。
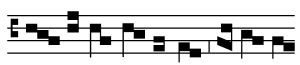
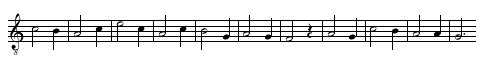
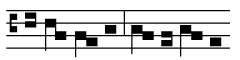
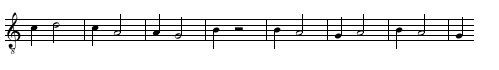
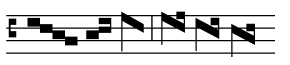
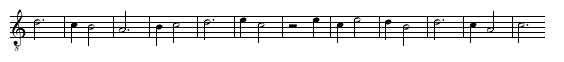
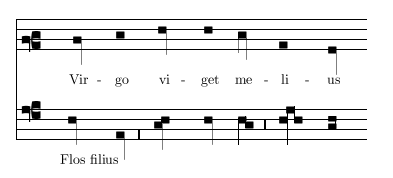
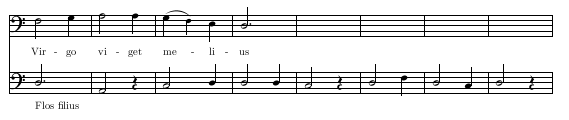
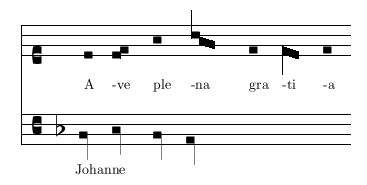
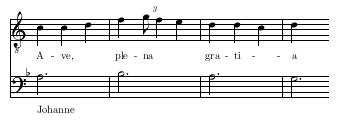
リガトゥラについては以上です。
●プリカ
プリカはある種の装飾を後ろに伴う音符です。(『計量音楽論』第六章参照。)例えば  は上行ロンガ・プリカと呼ばれ、ロンガの終わりにその音より上の装飾音が付けられることを示す音符です。例えば次のようにです。
は上行ロンガ・プリカと呼ばれ、ロンガの終わりにその音より上の装飾音が付けられることを示す音符です。例えば次のようにです。
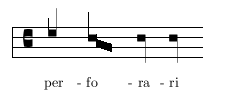
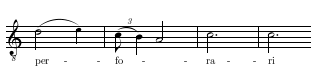
上行ロンガ・プリカ  の上下をひっくり返すと下行ロンガ・プリカ
の上下をひっくり返すと下行ロンガ・プリカ  になります。プリカと言ってもロンガであることに変わりはないので不完全化もします。次のように。
になります。プリカと言ってもロンガであることに変わりはないので不完全化もします。次のように。
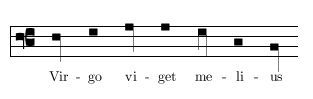
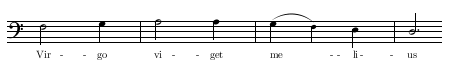
ロンガ・プリカの特徴は右側の縦棒の方が長いことです。これは、下行ロンガ・プリカ  を、普通のロンガ
を、普通のロンガ  に"ひげ"を付けたものと考えると憶えやすいかもしれません。
に"ひげ"を付けたものと考えると憶えやすいかもしれません。
※なお plica という語は「折れ目」「ひだ」という意味で、その名称は形状に由来します。
ブレヴィス・プリカは上行が  、下行が
、下行が  で、左側の縦棒の方が長いものです。例えば次のようです。
で、左側の縦棒の方が長いものです。例えば次のようです。
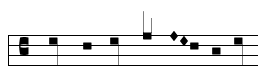
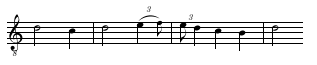
さて、プリカのリズムを上の例などでは、しっかり四分音符や三連音符を使って書いてしまいましたが、本当にそのように演奏されていたかはそれほど確かではありません。 (例えば、[Kanazawa]では、プリカは本当に装飾音符として現代譜に直されています。)
しかし、フランコの『計量音楽論』とほぼ同時代に書かれたマギステル・ランベルトゥス Magister Lambertus の『音楽論』Tractus de musica の説明によると、「完全ロンガ・プリカは本体にテンプス二つを、装飾音にテンプス一つを持ち、不完全ロンガ・プリカは本体にテンプス一つを持ち装飾音にその残りを持つ」と書かれているので、上のようなやりかたで良さそうに思えます。 またブレヴィス・プリカについてもこの完全ロンガ・プリカのアナロジーで上のような三連音符によるやりかたはもっともではないかという気もします。
音程についても、装飾音は隣接する2度上または下の音に上行あるいは下行するというので大体良いようですが、[Apel]のp.227の説明によると、上行プリカの次の音が2度上の音のときは、プリカの装飾音で3度上に上がってから2度上に下りる(下行プリカはその逆)というように書かれています。
単独音符のプリカでは、ときおり短い方の縦棒を省略した音符も使われます。すなわち、 は上行ロンガ・プリカを、
は上行ロンガ・プリカを、 は上行ブレヴィス・プリカを、
は上行ブレヴィス・プリカを、 は下行ブレヴィス・プリカを表します。(ここに下行ロンガ・プリカが無いのは何故でしょうか?)
は下行ブレヴィス・プリカを表します。(ここに下行ロンガ・プリカが無いのは何故でしょうか?)
リガトゥラにもプリカは存在します。(『計量音楽論』第八章参照。)作り方は簡単で、リガトゥラの最後に上向きまたは下向きの縦棒を付ければ良いだけです。
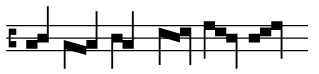
ここで注意しなくてはならないのは、上に示したものは全てクム・ペルフェクツィオネであることです。(したがって、終わりの音符はすべてロンガです。)まぎらわしいのは上行プリカで、例えば次です。
 = B-L plica,
= B-L plica,
 = B-B, (
= B-B, (
 = B-L)
= B-L) では、シネ・ペルフェクツィオネのリガトゥラのプリカを作るにはどうしたらよいかというと、上行も下行も終わりを斜形にします。
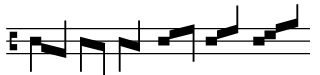
フランコ式記譜法でリガトゥラの終わりに斜形の上行形が用いられるのはこのときだけのようです。
|
[2]
|












